 |
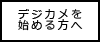 |
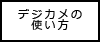 |
 |
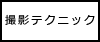 |
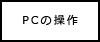 |
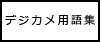 |
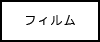 |
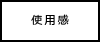 |
レンズの選び方
デジタル一眼レフやミラーレス一眼を使っていると、レンズを交換してみたくなるかもしれません。ただ、たくさんあるレンズの中から何を選べばいいのやら、と言う方も多いのではないかと思います。
ここでは、EDレンズは色収差の修正に有効である、非球面レンズは球面収差の補正に有効であるといった、ギミック的な説明や、解像度がという画質面的な説明はあまり扱わない方向で考えています。
もちろん、EDレンズが使われていてコーティングも逆光に強いナノクリスタルコートがというギミック面なんかも、レンズ選びの楽しみとしては大きいと思いますし、画質も気になると思いますが画質などは、レンズごとに大きく異なるので、そのレンズのレビューや実際に撮影された写真をみるのが一番だと思います
ここでは、カメラ本体とセットで販売されることが多く、持ってる人も多いと思われる普及帯クラス標準ズームレンズにプラスαをくわえるか、買い換えでの強化など普及体クラス標準ズームレンズを基本軸として、考えていきます。
35mm換算焦点距離で24-85mm前後、F値は3.5-5.6あたりのレンズが普及帯クラス標準ズームレンズとして多く使われています。
特徴としては、そこそこ扱いやすい広角から中望遠までを大体カバーしている点、標準域の3倍ズーム程度(*なん倍ズームは、望遠焦点距離÷広角焦点距離)と、あまり無理をしないズーム範囲のため、無理の少ない設計で比較的軽く小型なレンズが多いのもこのクラスの特徴です。一言で言えば、普段使いで使いやすいレンズといえます。なので、まずはこのレンズでたくさん撮影をしてみてください
使っていくうちに、近づけない場所、例えば花壇のちょっと奥の方の花を大きく撮りたいとか、もっと広い範囲を写したいとか、もっと近くによってアップで撮影したいとか、背景を大きくぼかしたい、または被写体ぶれが気になるシーンが多いから、成功率を上げたいなど欲求不満が出てきたら、いよいよ交換レンズを考える段階になったと言えます。
F値や35mm換算焦点距離別に、いくつかレンズをまとめてみました。*メーカーによって焦点距離の違いはあるので、大体こんなところという感じで分けています。
ズームレンズは表にまとめてみました。()内はAPS-Cで同等の「画角」が得られる焦点距離を書いています、APS-Cの焦点距離の場合、被写界深度(ぼけ)の傾向は小さくなりますが、極端に特徴がずれることは少ないと思いますので、そのままその特徴を読んでも大丈夫です。
| 広く写る←写る範囲→大きく写る 深い←被写界深度→浅い |
||||||||||
| 18mm (12mm) |
24mm (16mm) |
28mm (18mm) |
35mm (23mm) |
50mm (33mm) |
70mm (46mm) |
85mm (56mm) |
135mm (90mm) |
200mm (133mm) |
300mm (200mm) |
|
| F3.5-5.6
・軽量、小型 |
普及帯標準ズーム 旅行などで使いやすい画角をカバー |
|||||||||
| 超広角ズーム 広い風景を一枚の写真に写せる 後ろに退けない室内で広く写せる 遠近感を強調した撮影ができる |
||||||||||
| 普及帯望遠ズーム 近寄れない被写体を大きく写したい時 圧縮効果で密度を上げて見せたいときに 望遠端は、暗くぶれやすいので注意 |
||||||||||
| 高倍率ズーム 画質より便宜性を重視したレンズ レンズ交換の手間を減らしたい時に便利 望遠端は暗くなるので、ぶれやすい |
||||||||||
| F4.0通し
・比較的軽量で機動性に優れる |
中口径標準ズーム 特徴や向いてるシーンは、普及帯標準ズームに近い 望遠側が明るいため、ぶれにくい |
|||||||||
| 中口径超広角ズーム 特徴は超広角ズームに近い |
||||||||||
| 中口径望遠ズーム 近寄れない被写体を大きく写したい時 圧縮効果で密度を上げて見せたいときに 大きなぼけが楽しめる あまり重くなく、機動力に優れる |
||||||||||
| F2.8通し
・プロ、ハイアマ向けの上位レンズがほとんど |
大口径標準ズーム 室内など、やや暗い環境でも、ぶれにくいため 室内の撮影が多い人におすすめ フルサイズでは、望遠側で大きなぼけが得られるため 背景をぼかしたポートレートも楽しめる |
|||||||||
| 大口径超広角ズーム 特徴は超広角ズームに近い |
||||||||||
| 大口径望遠ズーム 近寄れない被写体を大きく写したい時 圧縮効果で密度を上げて見せたいときに 1kg超の重量級だが手持ち撮影も可能な重さ 非常に大きなぼけが楽しめる ぶれにくい |
||||||||||
単焦点レンズ
単焦点レンズの多くは、ズームレンズより明るいレンズが多く、また画質を上げやすいため高画質なレンズがそろっているので、たくさん撮影してるうちに自分はこの焦点距離の撮影が非常に多いなとか、好きな焦点距離がわかってきたら、単焦点レンズに手を出すのもありだと思います。
広角~中望遠(28~85)
標準ズームでカバーされる領域のレンズですが、この領域の単焦点レンズはトップクラスの明るさがあり、被写界深度の自由度という面でプラスαを加えることが出来るレンズが多いです、価格も一部を除けば、10万を超えるようなレンズがなく、手を出しやすいとも言えます。
| 広く写る←写る範囲→大きく写る 深い←被写界深度→浅い |
|||
| 28mm (18mm) |
50mm (33mm) |
85mm (56mm) |
|
| F1.8
・安価 |
28mmF1.8広角 記念撮影でランドマークを収めやすい 後ろに退けない室内で広く写せる 十分明るく、室内でもぶれにくい |
||
| 50mmF1.8標準 見た目に近い自然な写り 望遠的にも広角的にもできる |
|||
| 85mmF1.8中望遠 大きなぼけが楽しめる 人物撮影などに使いやすい画角 |
|||
| F1.4
・やや高価 |
28mmF1.4広角 主な特徴は、28mmF1.8とほぼ同じ F1.8の上位レンズ |
||
| 50mmF1.4標準 主な特徴は50mmF1.8とほぼ同じ F1.8の上位レンズ |
|||
| 85mmF1.4中望遠 被写体を引き立てる大きなぼけと 人物撮影がしやすい画角の持つため ポートレートレンズと呼ばれる |
|||
望遠(300mm~500mm超)
このクラスのレンズは、野鳥やスポーツなど近寄ることが困難な被写体を撮影するときに用います。とくにあまり近づけない小鳥など撮る場合は500mm以上がほしくなるようです。
また、このクラスは非常に高額なので、APS-Cサイズで考える方が現実的な価格となります。
例:300mmF4(18万円)をAPS-Cに取り付けると、450mmF4相当となり、フルサイズの500mmF4(117万円)に近い画角が得られる。
| 広く写る←写る範囲→大きく写る 深い←被写界深度→浅い |
||
| 300mm (200mm) |
500mm (333mm) |
|
| F4
・500mm以上の超望遠では明るいレンズ |
300mmF4望遠 スポーツ撮影で大きく撮影したいとき 高感度に強い機種ならば 室内スポーツにも対応可能 |
|
| 500mmF4超望遠 小鳥のような、近づくのが困難で、かつ小さい被写体など 望遠でも十分大きく撮れない時に |
||
| F2.8
・室内スポーツ向け |
300mmF2.8望遠 室内スポーツ向き APS-Cサイズ(200mm)では10万円台だが フルサイズ(300mm)では70万円と非常に高額 |
|
マクロレンズ
被写体に近寄って撮影が可能なレンズ、多くの場合、撮影倍率1倍ぐらいの撮影倍率を持っています。(通常のレンズは、おおよそ0.3~0.125倍)また、近寄って撮影したときにも画質の低下が少ないように設計されているのも特徴なので、もっと近くによって大きく写したいという方におすすめです。
注意点としては、マクロ撮影は非常にぶれやすいので、基本的に三脚を使った撮影となります
| 広く写る←写る範囲→大きく写る 深い←被写界深度→浅い |
|||
| 50mm (33mm) |
105mm (70mm) |
200mm (133mm) |
|
| F3.5 | 200mmF4マクロ ワーキングディスタンス(被写体とレンズまでの距離) が長いので、昆虫のように近寄りすぎると逃げて しまうような被写体向き |
||
| F2.8 | 50mmF2.8マクロ ワーキングディスタンスが短く ファインダーを覗きながら 被写体に手がとどくため 位置の微調整がしやすい |
||
| 105mmF2.8マクロ ワーキングディスタンスもそこそこ保るため レフ版などでライティングがやりやすい テーブルフォト向き |
|||
全部のレンズを扱うことは無理なので、ややおおざっぱな分類になりましたが、レンズを追加購入する参考になれば、うれしいです。
おすすめ記事